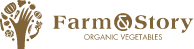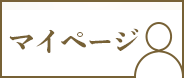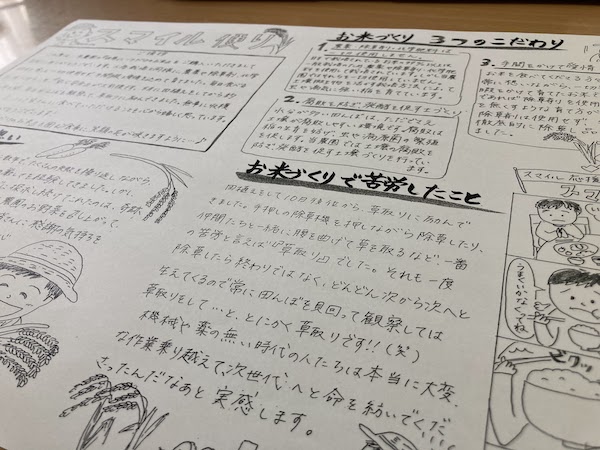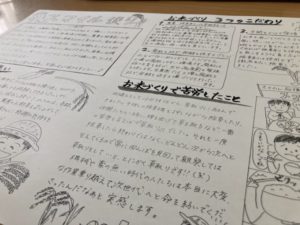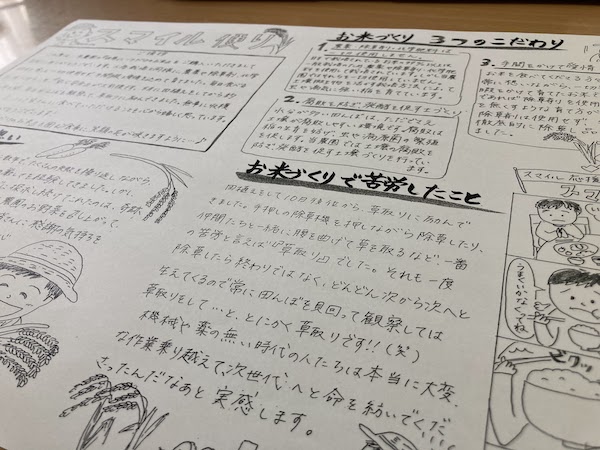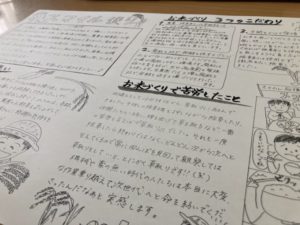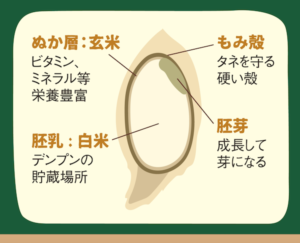冬になると我が家では
毎日人参が食卓に出てきます。
先日、農場長が大好きな
人参でステキなステーキを
焼きました。

米油や良質なオリーブオイルで
両面を焼いて、自然塩をパラリと
振りかけるだけです。
生のままいただくよりも
グッと甘みが増して驚きます。
あっという間に1本分
食べてしまいました。
人参は様々な料理に使えるので
常に冷蔵庫に常備しておきたい野菜の
一つです。
できるだけ長い期間人参を
食べられるように
どういった保管方法が良いかを
これまで色々試してきました。
今日は皆さんにも
人参を美味しく保存するコツ
をお伝えしたいと思います。
ぜひ参考になさってください!
保存のポイント
■冬場は常温でもOK
■夏場は冷蔵庫で保存
■常温保存よりも冷蔵の方が持ちが良い
冬場の常温保存の仕方
1.
葉を切り落とし、
水洗いした後、
水気をしっかり拭いて
一本ずつ新聞紙に包む。
2.
1.で包んだものを袋に入れ、
更にダンボールなどに入れて
暖房の効いていない冷暗所で保存。
(暖房の効く部屋はNG)
冷蔵保存の仕方
1.
常温保存の手順1.と同じ。
2.
保存ビニル袋に入れて
立てた状態にして冷蔵庫の
野菜室で保存。
冷凍保存の仕方
1.
好きな形・サイズに切って
サッと茹で、ザルにあけて冷ます。
2.
冷めたら
キッチンペーパーなどで
水分を拭き取り、
冷凍用保存袋に入れて冷凍保存。
▶︎サラダの具にしたり、
お弁当のちょっとした彩にも使えます。
===========
まとめ
===========
人参は水分や湿気が大の苦手です。
ですが、乾燥にも敏感・・・。
水分をよく拭き取って
保湿して保管する、
というのが共通するポイントです。
保存中、新聞紙の中身の
人参を適度にのぞいてみて
傷んでいないか?
を確認することをお勧めします!
冷蔵庫のスペースが
空き次第、常温から
冷蔵庫に移し替えたほうが
より一層長期に美味しさを
保つことができます。
*
*
ぜひ参考になさってくださいね♪