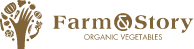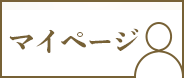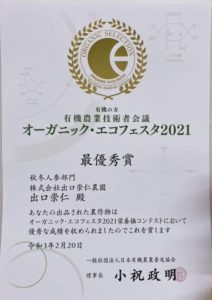シトシトと潤いの雨。東海地方も梅雨入りしました。
今年は統計史上2番目に早い梅雨入りだそうです。
平年より21日も早いのです。約3週間ですね。
こんなに早い梅雨入りは生まれて初めてです。
農家としてももちろん初めて。
今年はどんな気候になるのか?若干心配ではありますが、
今日できることをただひたすらに全力投球あるのみです!

さて、先月のブログに綴った『発酵タマネギ』にはトライされましたか?
冷蔵庫に常備してあるとどんな料理にもサッと使えるのでハマるとやめられません♪
今日は引き続き玉ねぎネタです。(^o^)/~~
新玉の季節なのでスライスしてサラダにして食べることが多いでしょうか♪
”美味しいタマネギスライスのコツ”をぜひお伝えしたくなりました!
栄養を損なわない調理のポイントをしっかり押さえていきましょう♪
【玉ねぎスライスのコツ】
(1)
玉ねぎの皮を剥いて縦半分にカットする。
(2)
ヘタの部分を上にしてスライサーでスライスしていく。
(この向きが大事!!うまく辛味が抜けます)
(3)
スライスした玉ねぎをバットや平たいザル全体に広げる。

最低でも20分。
可能であれば1時間置いておく。
※全体がまんべんなく空気に触れるよう、時々混ぜて重ならないようにする。
●ポイント●
1)
絶対に水にさらさないこと!水にさらすと、ビタミンB1などの
水溶性の栄養素が流出してしまいます。
2)
ヘタの部分はみじん切りにしたり、お汁の具にして食べること!
ここに栄養が沢山詰まっています◎
次に、この玉ねぎスライスを使ったレシピのご紹介です。
【今が旬!!カツオのたたき】
~タマネギスライスをのせて~

《材料》
・カツオのたたき 1さく
☆酢 100cc
☆しょうゆ 100cc
☆みりん 50cc
・新玉ねぎ 1個
☆ニンニク 小2~3粒
※酢:しょうゆ:みりんは 2:2:1の割合
《手順》
(1)
新玉ねぎをスライスのコツを参考にスライスして空気にさらす。
(2)
ニンニクをスライスし、カツオのたたきは約8mm~1cm位の幅に切り分ける。
(3)
⭐︎印(酢・しょうゆ・みりん)を調合し、切り分けたカツオのたたきと
スライスしたニンニクを30分程漬け込む。(冷蔵庫)
(4)
新玉ねぎスライス半分量を皿に敷き、カツオのたたきを並べ
その上に新玉ねぎスライスの残りをのせる。
(5)
漬け込みタレを適量とニンニクを上からかけて完成。
●栄養ミニ知識●
カツオは血液をサラサラにするEPAや、コレステロール値を下げるDHAが豊富。
体内で生成できない必須アミノ酸もバランス良く含んでいます。
血合には赤血球作りに役立つビタミンB12が多いので
貧血気味の方にもオススメです♡
*
*
ちなみに私は魚料理の中で一番好きなのが、このカツオのタタキレシピなのです!!
実母秘伝のレシピなので実家のことを思い出します。
私も母のように子どもの記憶に残る美味しいごはんを作り続けたい
と、思っています♪