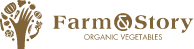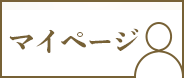先週の節分の日に豆まきはされましたか?
我が家では息子(2歳)が生まれて初めて本格的な豆まきをしました。
本格的と言っても、私が鬼役で玄関から入ってきて
父親と一緒に『鬼は外~!』
と豆をまく、普通のやり方なのですが。(^^;)
鬼を退治できて息子は誇らしげでした。
そして、恵方巻ではないですが、ちらし寿司を作ってみんなで食べました。
にんじんの形を表してみました♪

【にんじん畑 通信】なのでにんじんのお話がメインなのですが、
にんじんにんじんと、にんじんしか出てこないので、
皆さんがにんじんを嫌いになってしまわないか?
と、少々心配ですが今日もにんじんのことをお話しさせてください(^o^)/
当農園のにんじんの生育を『にんじん成長記』で綴ってきました。
前回のブログでは11月の様子をお伝えしています。
次回12月(最終)の様子をアップする予定です。
その前に、ダイジェスト版として2020,6~11月のにんじん畑の様子をまとめてみました!
2020年度のにんじん成長記録を共に振り返っていけたらと思います。
●6月:あえて草を生やす土づくり

2019年度度重なる豪雨の影響で一部の畑が水没。
この苦い経験をきっかけに「水はけ」の良い土へと土壌改良を決意しました。
あえて草の種を蒔き、土の深いところまで根を張らせて土の中を耕す作戦。
●7月:長~い梅雨

2020年の梅雨は本当に長かったです。
6月に蒔いた草の種が発芽してからこんなにも成長!!
梅雨が明けないことには次に進めないので早く明けないかな?
とヒヤヒヤしていました。
●8月:肝心要の種蒔き

8月ようやく晴れが続き、『太陽熱養生処理』という太陽の熱で土を改良していく方法で
土づくりが完了。
そして、ようやく人参の種蒔きへ。蒔いてからから1週間は水やりが欠かせません。
芽が出ますように!!!
●9月:芽が出た!!

この芽を確認するまでソワソワドキドキ心配と期待が心の中でグルグル回り続けます。
でも2020年もこの芽を見られて本当に良かった!!
感動しました。
この後、鬼の草取りが始まるのですが・・・
●10月:草取り&間引き

夏~秋にかけては草の成育の勢いがすごいのです…。
人参の芽が草に負けてしまわないように1本ずつ除草していきます。
同時に間引きをして人参同士の間隔を空けていきます。
●11月:成育見守り

割と暖かい秋でした。
なので人参も引き続き元気にグングン大きくなっていきました!
間引いた葉付き人参を近隣の直売所にて販売しました!
12月以降は収穫です。
寒さが深まっていけば行くほど人参が甘くなり、旨味も増しておいしくなっていきます♪
次回は12月の収穫の様子をお届けできたらと思っています!
それでは、また次回を楽しみにお待ちください(^_^)♪