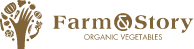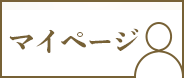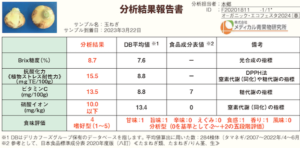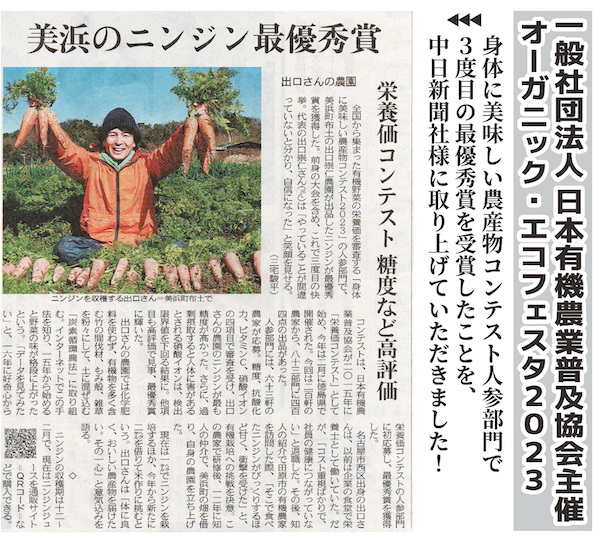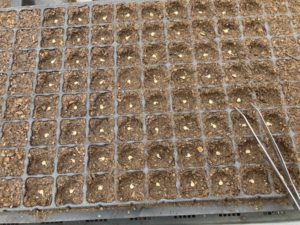今年は夏の催し物が
全国各地で開かれて、
日本の夏が戻ってきた!
という賑やかな夏でした。
近所の花火大会も開催されて
会場に集う人たちの笑顔が印象的でした。
感染症の流行から3年以上が経ち、
ようやくこういった夏の楽しみを
満喫できるようになり、
なんだか気持ちが開放されたように感じました。(^^)
これからもお野菜モリモリ食べて
健康に過ごしていきたいものです。
さて、今日は月末なので
にんじん成長記2023をお届けしたいと思います。
時は遡ること・・・
6月のにんじん畑の様子
6月は梅雨の晴れ間をぬって
人参栽培用の圃場の耕運と草刈りを進めていました。
圃場によっては緑肥を撒いて
草を育てているところもあります。

まだ暑さがそこまで厳しくなかったため、
草の勢いはこれからですが、
草の根の力によって、
地中を深いところまで耕してもらいます。
6月はどちらかというと
田んぼの草取りに注力し、
毎日泥だらけになって作業をしていましたよ!
==============
必要不可欠な仲間のチカラ
==============

作業スペース拡大と
スタッフの休憩場所にとハウスを建てました!
天井部分が透明ではないため、
日光も遮ることができます。
横のビニールをオープンにすれば
真夏でなければ涼しく過ごせます。
これまで農場長一人だけで
作業をしてきた時期もありましたが、
こうしてスタッフが増えていくと、
一人でやっていたことの2倍どころか
3倍4倍という量をこなすことができます。
改めて「自分以外の人の力」が、いかに重要かを実感しています。
私たちと一緒に多くの方の健康を支える
栄養満点な野菜を育ててくれる
スタッフの育成もがんばっていきます!
農業の担い手が減っている今、
私たちのような若手農家が
踏ん張って農業界を盛り返していきたいと思います!
追伸:

写真:人参のお花
今年も開花しました♪