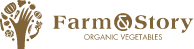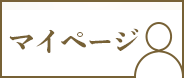各地で桜が咲き始め、
お散歩やピクニックが
楽しみな季節になりました!
新玉ねぎのご注文も
たくさんいただきまして
誠にありがとうございます。
新玉ねぎは人参と異なり
旬が一瞬で終わってしまいます。
おそらく4月中旬頃には出荷
終了となるのではないかと
予想しています。
迷い中の方はお早めに
ご予約くださいね。
今年は人参に引き続き、
「まとまった量の新玉ねぎありませんか?」
とお声がけいただいていて、
旬が終わってしまう前に
大急ぎで出荷です!!
まさに新玉ねぎは、
早い者勝ちです^^
さて、今日の本題は!!
1月のにんじん畑の様子のレポートです。
1月に入ってからも
人参の収穫と出荷をスタッフ総出で
がんばりました!

今年は新しく借りて
栽培をスタートさせた圃場が多く、
収穫まで結果がわからない
ドキドキ感がたまりませんでした。
新しい圃場においては、
1つの圃場の中でも
場所によって生育が
まばらなことがわかったり、
排水具合や水もち、
日当たりなど夏から冬にかけての
各圃場の様子がようやくわかってきました。
これで次の栽培は
もう少し工夫を凝らして
より良い品質の人参を
お届けすることができると思います!
新たな挑戦、春人参
今年は新しい挑戦として、
春人参の栽培にチャレンジしています。
12~2月の寒い時期に種をまき、
ビニールトンネルマルチをかけて
小さなハウスを作り、加温します。

20日くらい経つと
ニョキっと芽が出てくるのです・・・!

発芽を確認した時は、
「芽が出た〜〜〜!!!」と叫びました。(笑)
これからスクスクと
育ってくれることを
楽しみにお世話を続けていきます。